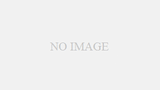2025/06/08 北海道新聞
寺尾紗穂の愛し、読書(かなし、どくしょ)
「平等」考える 盲ろう者の半生記
「見えない、聞こえない」。門川紳一郎『ぼくのデフブラらいふ』(ころから)は盲ろう当事者である著者による半生記だ。盲ろう者の場合、手話一つとっても、触手話という形で両手に触れながら意味を理解する。見て理解する通常の手話とは伝え方が大きく異なり、本書に絵と文を寄せた金井真紀によれば「せっせーせーのよいよいよい」のような柔らかい雰囲気だという。
それでも米国での大学院時代は、触手話通訳も著者自身も授業内容の伝達、理解に非常に体力を要し、授業内で休憩時間が設けられたという。盲ろう者が学ぶとき、そのような手段があるとは本書を読むまで想像もできなかった。
周囲に助けられて、目標を達する。順調な経験ばかりではない。「盲ろう者友の会」と銘打たれた団体でも、多数派の盲者、ろう者の中で盲ろう者の意見は反映されない実態や盲ろう当事者のみの団体をつくって代表になっても、当事者以外のスタッフに経営権が移ってしまうという話からは、重複障害者の立場の弱さが浮き彫りになる。
たしかに彼らには「できないこと」や「できるとしてもそれにかかる手間や人手」が多く見える。ただ門川が書くように障害者の「自立」を「自分が決めた目標を、自分自身での判断で選択した社会資源やサービス等を利用して、達成する」こととする定義は、平等とは何かという重要なテーマと結びついており、見過ごされえてはならないものだ。
ネット上では複数人の介助を必要とする障害者などに対して多額の税金で生きている、といった中傷が聞かれ、差別的発言が公然と語られる。「平等」とは何か、社会に正しい理解が根付くのはいつだろうか。(シンガー・ソングライター、エッセイスト)