書名:あきらめる勇気ー「見えなくなった」僕を助けてくれたのはー
著者:松永信也
本書の著者は目の難病のため、30代後半で視力に異常を感じ始め、見えなくなる恐怖からそれまで働いていた児童福祉施設を退職する。1年ほどの間は、まるで「抜け殻」のように、ただ息をしているだけだった。40歳の頃に失明してからは悲しみや苦しみを味わい孤独感や挫折感も感じた著者は、「この世から逃げ出したい衝動にかられたこともあった」と言う。
それでもなんとか立ち直り、生活訓練を受け再度の社会復帰を目指して就職活動に励むが、社会の厳しい現実に直面することになる。しかし、そんなことにもめげず、少しずつ自分自身を取り戻していく姿は感動的だ。
社会復帰を果たし、福祉の授業で招かれた小学校で、子供たちに「白い杖を持った人たちを見かけた時にどう思いますか」と尋ねたところ、9割から「かわいそう」という答えが返って来たそうだ。
子供たちの率直な答えからもわかるように、「見えない」ことは「かわいそう」なこと、「怖い」ことというのが、社会のおおかたの固定観念なのだろう。
「見えない」ことは「あきらめる」しかない。「あきらめる勇気」というものは、自分自身を変えることはできても、社会を変えることはできないと、著者は解く。
それでも、見えていた頃の「社会参加の夢」の実現に向かって、メッセージを発信し続けるためにブログを書き始める。2012年からこつこつ書き溜めたブログを、整理し編集したのが本書だ。
「見えなくなって良かったこと」は、「優しい人達に出会えること」と評する著者はどこまでも謙遜だ。「見えないこと」を勇気を持ってあきらめた著者ならではの感想なのだろう。そんな著者の姿勢に感銘を受けた。
「見えない」こと、「聞こえない」こと、あるいは、「見えないし聞こえない」ことは、未だに「かわいそう」とか「大変」といったように世間では思われているんだなと、再認識させられる。
そういえば、私自身も幼い頃から視覚と聴覚に障害があり、障害と向き合いながら生きてきた。いつの頃からだったろうか、「見えない、聞こえない」ことをあきらめ、自分なりに生きて行く道を選ぶようになっていた。つまり、見えなくて聞こえないのが当たり前というように。本書を読んでいると、著者の生き方とどこか通じるところがあり、懐かしさを感じる。
40歳で失明するまでは、健常者であった著者の経験談、人生論は説得力に富む。しかも、平易な文章で丁寧につづられた本書はだれにとっても読みやすく読み応えのある1冊だ。
本書を通じて著者は次のように述べている。「見えていた頃のぼくも今のぼくも、やっぱりぼくはぼくなんだと自信をもって言えます。」

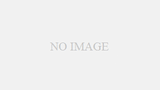

コメント