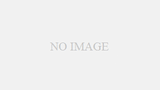言語について
「言語」には、英語等の「音声言語」の他、聴覚に障害のある人の「手話」があります。多くの国では、「手話言語法」という名実共に「手話」の法律があります。我が国でも、全日本ろうあ連盟の15年以上にも及ぶ運動の結果、「手話施策推進法」が成立しました。法律の名称には満足できませんが、手話の理念を規定した法律が国会で成立したことは評価できるでしょう。同法は6月25日に施行されました。
もちろん、法律ができたから万事OKという訳ではありません。むしろ、これからこの法律を社会に周知し、聴覚障害者がいつでもどこでも手話によるコミュニケーションが当たり前にできるようになることが大切です。そうなるためには、私達はこれからも社会に働きかけていかなければならなりません。
盲ろう者とコミュニケーション
ところで、世の中には「視覚も聴覚も使えない」、いわゆる「盲ろう者」(視聴覚重複障害者)がいます。2024年の厚生労働省による実態調査では、盲ろう者は全国に約1万人いるという結果があります。(2012年の調査では1万4千人)
盲ろう者の場合、視覚と聴覚に障害があるため、コミューションの方法はこれらの感以外、つまり触覚や嗅
盲ろう者のコミュニケーション手段の種類
では、盲ろう者のコミュニケーション方法にはどんなものがあるのでしょうか?
コミュニケーションの手段として、手話や点字、筆記などがかんがえられます。
手話について
手話は「視覚的表現」なので、目で見るものだが、見えない盲ろう者は相手の手話を手で触って読み取る方法があります(触手話)。弱視で少し見える場合には、盲ろう者の見やすい位置で手話を表す等の工夫をします(弱視手話)。触手話の場合は、相手の手の動きからしか情報を得ることができませんし、弱視手話の場合も、見え方によっては受信する情報が制約されます。(聴覚障害だけの場合は、手話だけでなく全体的な雰囲気なども見て理解することができる)
字につ
点字
点字は視覚障碍者が読み書きに使う触覚文字で、1825年にパリの視覚障害者ブライユが考案したのが公式に知られている最初の点字です。
日本では1887年(明治20年)に、教員の石川倉次がブライユの点字を日本でも使えるように研究を始めました。
そして、1890年(明治23年)11月1日に、日本の視覚障害者の文字として制定され、この日は「日本点字記念日」となりました。
日本語点字は6つの点の組み合わせで構成されます。
点字筆記具に「点字タイプライター」があり、アメリカのパーキンスブレイラーは有名です。パーキンスは6つのキーとスペース、バック、改行キーの9コのキーで成り立っています。これにヒントを得て考案されたユニークな盲ろう者のコミュニケーション方法が「指点字」です。「指点字」は、両手合わせて6本の指をパーキンスブレイラーの6つのキーに見立て、点字で言葉を伝える方法です。
しかし、「指点字」はこれを受信する技術が高度なため、利用する盲ろう者は少ないのが実情です。
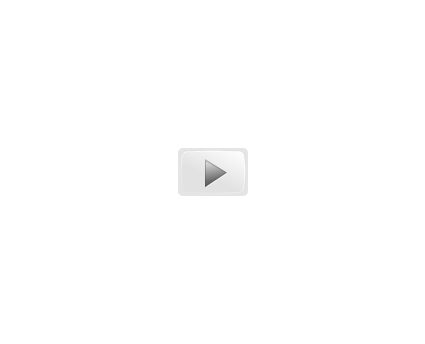
筆記について
神に書く原始的な筆記(手書き)からパソコンやタブレットを使う場合など様々な方法があります。
道具を用いない方法として、盲ろう者の手のひらなどにかなを書く方法があります。「手書き文字」とよばれているこの方法は、文字さえ知っていればだれとでも使えます。
デメリットとしては、
ひとつひとつ文字を書いていくため、時間がかかって会話が続きにくいことがあります。
さぁ、あなたもコミュニケーションスキルを磨いて、いろんな人とつながってみましょう。